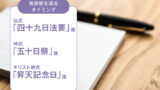香典返しは仏式の習慣として知られていますが、神式でも「御玉串料」などへの返礼として品物を贈る文化があります。神道では、香典返しの時期や品物の選び方、熨斗の表書き、挨拶状の内容に独自のしきたりがあり、五十日祭をはじめとする法要に合わせた返礼のタイミングも重要です。正しいマナーを理解し、故人を偲びながら適切に準備を進めることが大切です。この記事では、神式の香典返しの基本とマナーについて解説します。
>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

神式における香典返しの考え方

神式での香典返しの意味
香典返しは本来仏教の風習ですが、神式でも「御玉串料」「御霊前」「御榊料」をいただいた際、感謝の気持ちを込めて返礼品を贈る習慣があります。神式では、仏式の四十九日にあたる五十日祭を忌明けの節目とし、その後「偲び草」などの名目で香典返しを贈るのが一般的です。贈る時期は五十日祭後できるだけ早く、目安として一か月以内が適切とされています。遅れすぎると失礼にあたるため、早めの準備が重要です。
香典返しにおける基本的なマナー

贈る時期
神式では、仏式の四十九日にあたる「五十日祭」を忌明けの節目とします。そのため、香典返しは五十日祭を執り行った後、できるだけ早く、目安として一か月以内に贈るのが適切です。あまり遅くなると礼を欠くとされるため、事前に準備を進めておくことが望ましいです。また、当日の霊祭である五十日祭に合わせて引き物を用意する場合もあります。この場合は、事前に参列者の人数を確認し、必要な数を用意しておくとスムーズです。
返礼品の選び方と金額の目安
五十日祭を忌明けの節目とした後、感謝の気持ちを込めて贈る返礼品は、できるだけ早く、一か月以内を目安に準備するのが適切とされています。金額の目安は、いただいた「御玉串料」の三分の一から半額程度が一般的です。高額すぎる品を選ぶと、相手に気を遣わせてしまうことがあるため、相場を守ることが大切です。また、返礼品としては「形に残らないもの」が好まれ、食品や日用品が多く選ばれます。地域の習慣によって異なる場合もあるため、事前に確認すると安心です。
掛け紙の種類と表書き
香典返しの品には、適切な掛け紙を用いることが大切です。神式では、黒白または黄白の結び切りの水引がついた掛け紙を使用し、仏式で一般的な蓮の花の絵が入ったものは避ける必要があります。表書きには「志」または「偲び草」と記載するのが一般的で、一部の地域では「茶の子」という表記が用いられることもありますが、全国的には「偲び草」の方が広く使われています。名前の記載は、喪主の姓、またはフルネームを用いるのが基本です。
挨拶状の書き方
香典返しには、感謝の気持ちを伝えるための挨拶状を添えることが重要です。神式の挨拶状では、「帰幽」「五十日祭」「御玉串料」などの神道特有の言葉を使用します。また、仏式の「供養」「冥福」といった表現は神道では用いません。神式の正式な表現に則った挨拶状を用意し、相手に失礼のないようにしましょう。格式を重んじる場合は、奉書紙を用いた本格的なものを選ぶのが適切です。
挨拶状の例文
謹啓
先般 (続柄)(俗名) 帰幽に際しましては
ご多用の中にもかかわらずご会葬を賜り
かつご丁重なるご厚志を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げますおかげをもちまして○月○日に五十日祭を滞り無く相営みました
つきましては偲草のしるしまでに心ばかりの品をお届け致しましたので何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます本来であれば拝眉の上御礼申し上げるべきとは存じますが 失礼ながら書中を持ってご挨拶申し上げます
謹白
香典返しにおすすめの品物

食品
和菓子
和菓子は、日本の伝統的なお菓子であり、香典返しとして用いられることが多い品です。上品な甘さと落ち着いた風味が特徴で、幅広い世代に親しまれています。特に、どら焼きや羊羹、最中などの日持ちするものが好まれ、相手の都合に合わせてゆっくり楽しんでもらえる点が魅力です。個包装されているものが多く、分けやすいことからも、贈り物として選ばれることがよくあります。
洋菓子
洋菓子も香典返しの品として人気があり、特に焼き菓子は多くの方に喜ばれます。クッキーやフィナンシェ、マドレーヌなどは、しっとりとした食感と甘さが特徴で、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。洋菓子は比較的軽やかな味わいのものが多く、コーヒーや紅茶と相性が良いため、好みに合わせて楽しんでもらえるのも魅力です。個包装の詰め合わせを選ぶと、より贈りやすくなります。
お茶・コーヒー
香典返しには、お茶が定番の品として選ばれます。特に緑茶は、日本の弔事と深く関わりがあり、法要の席でも振る舞われることが多い飲み物です。日持ちがしやすく、多くの方に受け入れられるため、香典返しに適しています。紅茶やコーヒーも人気があり、紅茶は洋風の暮らしに馴染みのある方に喜ばれやすく、個包装のティーバッグタイプが便利です。コーヒーは幅広い世代に好まれ、特にドリップコーヒーやインスタントコーヒーの詰め合わせが贈り物として適しています。
調味料の詰め合わせ
料理をする方への香典返しには、醤油や味噌、オリーブオイルなどの調味料の詰め合わせが喜ばれます。普段使うものでも、老舗の醤油や天然醸造の味噌、エクストラバージンオリーブオイルなど質の高いものを選ぶと、特別感のある贈り物になります。最近では、トリュフ塩や高級だしパック、バルサミコ酢など、食卓を少し特別にする調味料も人気です。調味料は日常的に使うため無駄になりにくく、どの家庭にも馴染みやすい香典返しとして適しています。
日用品
石鹸・洗剤ギフト
洗剤や石鹸は、日常的に使う消耗品として香典返しに適しています。衣類用や食器用の洗剤は実用性が高く、家庭で重宝されます。石鹸は無添加や自然由来のものが人気で、肌に優しく香りが控えめなタイプが選ばれやすいです。どの家庭でも使いやすく、負担になりにくい贈り物です。
タオル
タオルは「悲しみを拭う」という意味が込められており、香典返しとして長年選ばれてきた品物です。特に白いタオルは格式があり、弔事の贈り物としてふさわしいとされています。今治タオルなどの上質なものを選ぶと、より丁寧な印象を与えることができます。
カタログギフト
香典返しに便利なカタログギフト
カタログギフトは、受け取った方が好きな品を選べるため、香典返しに適しています。食品や日用品、趣味に関する品まで幅広く揃っており、年代を問わず喜ばれることが多いです。相手の好みが分からない場合でも安心して贈ることができ、迷ったときにも選びやすい品のひとつです。香典返しのひとつです。
>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」
神式の法要について

霊祭(みたままつり)の流れ
神式の霊祭は、亡くなった翌日に行う「翌日祭」から始まり、その後十日ごとに「十日祭」「二十日祭」「三十日祭」「四十日祭」「五十日祭」と続きます。かつてはすべての霊祭を行うのが一般的でしたが、現在では翌日祭、十日祭、五十日祭を中心に行われることが多く、十日ごとに行う霊祭の中には実施しない場合もあります。
忌明けの節目
五十日祭が仏式の四十九日にあたり、忌明けの節目とされるため、多くの家庭ではこの日をもって神棚の封を解き、日常の生活に戻ることになります。また、五十日祭の翌日には「清祓の儀(きよはらいのぎ)」が行われることがあり、故人が清らかな霊として受け入れられたことを確認する儀式とされています。
式年祭
五十日祭以降の霊祭は「式年祭(しきねんさい)」と呼ばれ、仏教の年忌法要にあたります。一年祭、三年祭、五年祭、十年祭と続き、その後も節目ごとに執り行われ、長く故人を偲ぶ機会となります。特に一年祭は重要とされ、多くの家庭で親族を集めて丁寧に執り行われます。
まとめ

神式では、五十日祭を忌明けの節目とし、「偲び草」などの名目で香典返しを贈るのが一般的です。品物は消耗品や食品類が好まれ、相場はいただいた御玉串料の三分の一から半額程度が目安です。掛け紙には黒白または黄白の結び切りの水引を使い、「志」や「偲び草」と記載し、挨拶状には仏式の表現を避けた言葉を用いるのが適切です。神式では、故人を偲ぶ儀式があり、五十日祭のほか、一年祭や三年祭などの式年祭が続きます。正しいマナーを守り、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
香典返し・法要・法事の贈り物
香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」
香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。
カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。
ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。
>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」