法要や法事の際に参列者へ渡す「引き出物」は、単なる贈り物というよりも、故人を偲んで足を運んでくれた方々に感謝の気持ちを伝えるための大切な贈答品です。しかし、実際に準備を始めてみると、引き出物の金額の目安や品物の選び方、さらには地域による風習の違いや細かなマナーも絡んでくるため、戸惑う点も多いです。この記事では、法要・法事における引き出物の金額相場や品物選びのポイント、当日の作法や熨斗のルールについて解説します。
>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

法要・法事の引き出物(お返し)の金額相場

引き出物の一般的な金額相場
引き出物にかける金額の目安は、一般的に香典の3分の1から半額程度とされています。たとえば1万円の香典を受け取った場合は、3,000円から5,000円の品物を選ぶと、失礼がなくちょうど良いバランスになります。金額が高すぎると相手に気を遣わせてしまうこともあり、慎重に見極めることが大切です。
少額香典の場合の考え方
香典が少額だった場合には、2,000円前後の引き出物でも問題はなく、無理に高価なものを選ぶ必要はありません。引き出物はあくまでも感謝の気持ちを表すためのものであり、金額がすべてではないということを念頭に置いておくと良いでしょう。
地域による違い
地域ごとの慣習にも注目が必要です。例えば、関東では一品のみの引き出物が主流ですが、関西では二品以上を一組にする「組み物」の形式が一般的です。こうした違いを踏まえ、親戚や地元の葬儀社などに相談することも、準備をスムーズに進める上で役立ちます。
引き出物選びのポイントと注意点

引き出物の定番は「消え物」
引き出物に適しているのは、日常生活の中で使ったり消費したりできる「消え物」と呼ばれるものです。これは「不幸を残さない」という意味を込めて、法要にふさわしいとされています。
和菓子
羊羹、せんべい、あられなどの和菓子は、落ち着きのある雰囲気があり、年配の方にも受け入れられやすい品です。控えめで上品な甘さが法要の趣にもなじみ、個包装で配りやすい点も引き出物向きのポイントです。
洋菓子
クッキーやフィナンシェ、マドレーヌといった洋菓子は、若い世代を中心に幅広く喜ばれる人気の品です。見た目が華やかなものも多く、弔事用としては落ち着いたデザインのパッケージを選ぶことで、引き出物としての印象を整えることができます。
お茶・コーヒー
お茶やコーヒーは幅広い世代に親しまれている飲み物で、落ち着いた時間を連想させることから、弔事の引き出物としても人気があります。高級茶葉やドリップコーヒーの詰め合わせなど、上品で持ち帰りやすいものが多く、味や香りを楽しめるギフトとして好まれています。
タオル
タオルは実用性が高く、性別や年齢を問わず贈りやすい品です。今治タオルなど高品質なものを選べば、贈る側の気遣いが伝わりやすくなります。清潔感があり、派手すぎない色やデザインを選ぶことで、法要の場にふさわしい引き出物として仕上がります。
洗剤・石鹸
洗剤や石鹸は「清める」「洗い流す」といった意味合いがあり、弔事にふさわしいとされる実用品のひとつです。どちらも日常で必ず使うものでありながら、消耗品として残らないため、引き出物として選びやすい特徴があります。無香料や自然由来の成分を使用したもの、パッケージが落ち着いたデザインのものなど、上品で控えめな印象のものを選ぶと安心です。
引き出物としてのカタログギフト
最近ではカタログギフトの人気も高まっています。贈られた方が自分の好きな品を選べる仕組みで、年齢や性別を問わず対応しやすいという点が選ばれる理由です。特に遠方から参列する方には、軽くてかさばらないことも利点になります。
>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」
避けるべき品物
一方で避けたい品物もあります。祝い事で使われる鰹節や昆布、生のお肉や魚といった「四つ足生臭もの」は仏教的な意味合いから避けるべきとされています。また、赤や金といった華やかな包装も法要にはふさわしくないとされるため、落ち着いた色合いと品のある見た目を意識しましょう。
当日に引き出物を渡す正しいタイミングと対応

引き出物を渡すタイミング
引き出物は、法要の一連の儀式が終わり、お斎(おとき)と呼ばれる会食の後に渡すのが一般的です。このタイミングは場が落ち着いており、感謝の気持ちを自然に伝えやすいという理由から多く選ばれています。お斎を設けていない場合でも、法要終了後に参列者が帰るタイミングで手渡すのが自然な流れです。受付で渡す場合は会の始まりに干渉しないよう配慮し、式が終わってからの対応が基本です。
感謝の言葉を一言添える
引き出物を渡す際は、品物だけでなく一言の挨拶を添えることが大切です。「本日はご参列いただきありがとうございました。ささやかですが、お受け取りください」といった言葉をかけるだけでも、気持ちはしっかり伝わります。声のトーンや表情も大切です。形式的な言葉であっても、丁寧で穏やかな口調で伝えるだけで、より感謝の気持ちが伝わる場面になります。
スムーズに渡すための準備
引き出物は事前に人数分を用意し、受付や出口付近に整えて配置しておくと、当日の受け渡しがスムーズです。内容が異なる場合は、熨斗やラベルで区別すると渡し間違いを防げます。欠席者には後日郵送や訪問で渡すのが丁寧です。最後まで感謝の気持ちを伝えるつもりで対応しましょう。
掛け紙に関するマナーと注意点
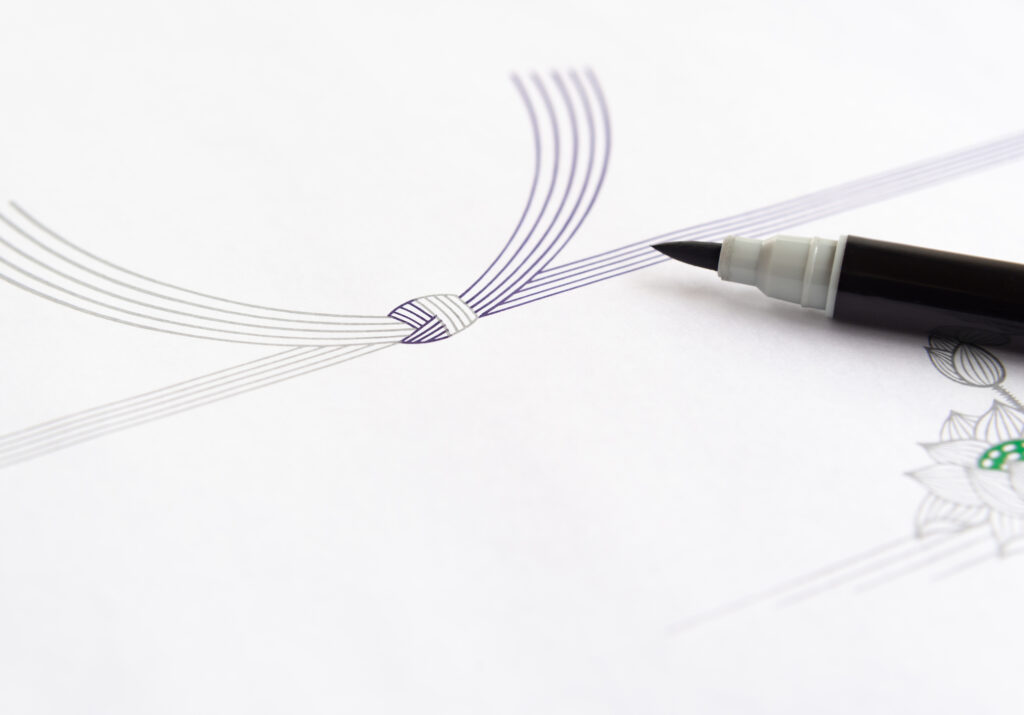
掛け紙の表書きと水引の選び方
法要の引き出物には、掛け紙をかけるのが基本です。弔事では「熨斗(のし)」は付けず、水引のみのシンプルな掛け紙を使用します。表書きには「志」と記すのが一般的で、感謝と哀悼の気持ちを静かに伝える意味があります。水引は、一度きりで終わることを願う「結び切り」を使い、色は地域によって異なります。関東では黒白、関西では黄白がよく使われる傾向があります。
掛け紙に記載する名前
掛け紙の下段には、施主である喪主の名字またはフルネームを記載します。誰からの贈り物かを明確にし、受け取る方に安心感を与えるためです。文字は毛筆や筆ペンなどを使い、落ち着いた字体で丁寧に書くのが理想です。印刷された名前でも問題はありませんが、できる限り手書きの方が気持ちが伝わります。
弔事の場に合う包装
包装紙は、法要の場にふさわしい落ち着いた色合いを選びましょう。白、グレー、淡い紫などがよく用いられ、柄も控えめで品のあるデザインが好まれます。赤や金といった派手な色合いや、祝い事を連想させる華やかな模様は避けるのが基本です。掛け紙や包装も含めて、感謝の気持ちを伝える大切な要素ですので、細部まで丁寧に準備することを心がけましょう。
まとめ

法要や法事の引き出物は、故人を偲び参列者へ感謝を伝える大切な贈り物です。金額の目安は香典の3分の1から半額程度で、品物は「消え物」やカタログギフトが好まれます。渡すタイミングは法要や会食後が基本で、感謝の言葉を添えて丁寧に渡すのが望ましいです。掛け紙はのしを付けず、表書きや水引の色は地域の風習に合わせ、包装も控えめで上品に整えましょう。形式だけでなく気持ちを込めることで、心の伝わる引き出物になります。
香典返し・法要・法事の贈り物
香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」
香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。
カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。
ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。
>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」


























