喪中にお正月を迎える際、多くの方が「おせち料理を食べても問題ないのか」と迷いがちです。喪中とは故人を偲びながら静かに過ごす期間とされ、日本ではこの時期に祝い事を避けるのが一般的とされています。特におせち料理は新年の喜びを象徴する料理であるため、その扱いには一定の配慮が求められます。宗教や地域によって違いもありますが、共通して守るべきマナーや考え方が存在します。この記事では、喪中に迎えるお正月の過ごし方とおせち料理の扱いについて詳しく解説します。
>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

故人を偲ぶお正月の過ごし方

喪中という期間の意味
喪中とは、親しい家族や親族の死を悼み、静かに過ごす期間のことを指します。日本ではこの期間、祝い事や賑やかな行動を控えることで、故人への敬意と哀悼の意を示す文化があります。一般的には故人の死から一周忌までの約1年が喪中とされ、特に2親等以内の身内が亡くなった場合には、この慣習を重んじる傾向が強くなります。
喪中にふさわしい正月の過ごし方
お正月には門松やしめ飾り、鏡餅、初詣、年賀状など、さまざまな祝いの行事が行われますが、喪中の場合はこれらを控えるのが通例です。特に「忌中」とされる四十九日(仏教)や五十日(神道)の間は、故人の魂がこの世にとどまっているとされ、祝い事を避けて慎ましく過ごすことが重視されます。
仏壇に故人の好物を供える
喪中のお正月には、故人が好きだった料理や飲み物を仏壇に供え、家族でその人を偲ぶ時間を持つことが心の支えになります。ゆっくりとした時間の中で、故人の思い出を語り合い、感謝の気持ちを新たにすることができます。
お墓参りで故人に新年の報告
新年のはじまりにお墓参りをして、故人に挨拶をすることも多くの家庭で実践されています。華やかな飾りやイベントを避けながらも、心を込めて手を合わせることで、故人の存在を身近に感じながら年明けを迎えることができます。
喪中における新年の食事

おせち料理は控える
おせち料理には、紅白のかまぼこ、伊勢海老、栗きんとんなど、新年を祝う意味が込められた食材が多く使われています。これらは色や形、味付けに至るまで祝いの雰囲気を持ち、喪中という厳粛な時間にはそぐわないとされています。そのため、喪中の正月にはおせち料理を控える家庭が多く、故人への敬意を表す行動とされています。
喪中でも取り入れやすい食事の工夫
喪中だからといって、すべての料理を禁じるわけではありません。祝いの意味を避けた控えめな食事内容であれば問題なく、新年を穏やかに迎えることができます。年越しそばは「長寿」を意味するとされ、縁起物ではあるものの派手さがなく喪中にも適しています。また、雑煮も紅白のかまぼこなどの具材を避け、味付けを抑えることで喪中に合った料理としていただくことが可能です。
ふせち料理で心を整える
近年では、おせち料理の代わりに「ふせち料理」と呼ばれる献立を準備する家庭も増えています。ふせち料理は、派手な彩りや祝いの意味を持つ食材を避け、精進料理を基本とした野菜中心の落ち着いた内容で構成されます。故人を想いながら、感謝と静寂の中で新年を迎えるという考えが込められており、喪中の食事マナーとしてふさわしいです。
宗教や地域ごとのおせちの考え方
喪中のお正月に対する考え方は、宗教や地域の風習によっても異なります。たとえば、浄土真宗では「亡くなればすぐに成仏する」という教義があり、喪中という意識を持たず通常どおり正月を祝う家庭もあります。キリスト教でも、死を神のもとへの旅立ちととらえるため、新年の祝いが問題とされないことが多いです。このように、信仰や地域の文化によってマナーの解釈も変わってきます。
喪中における礼儀と周囲への配慮
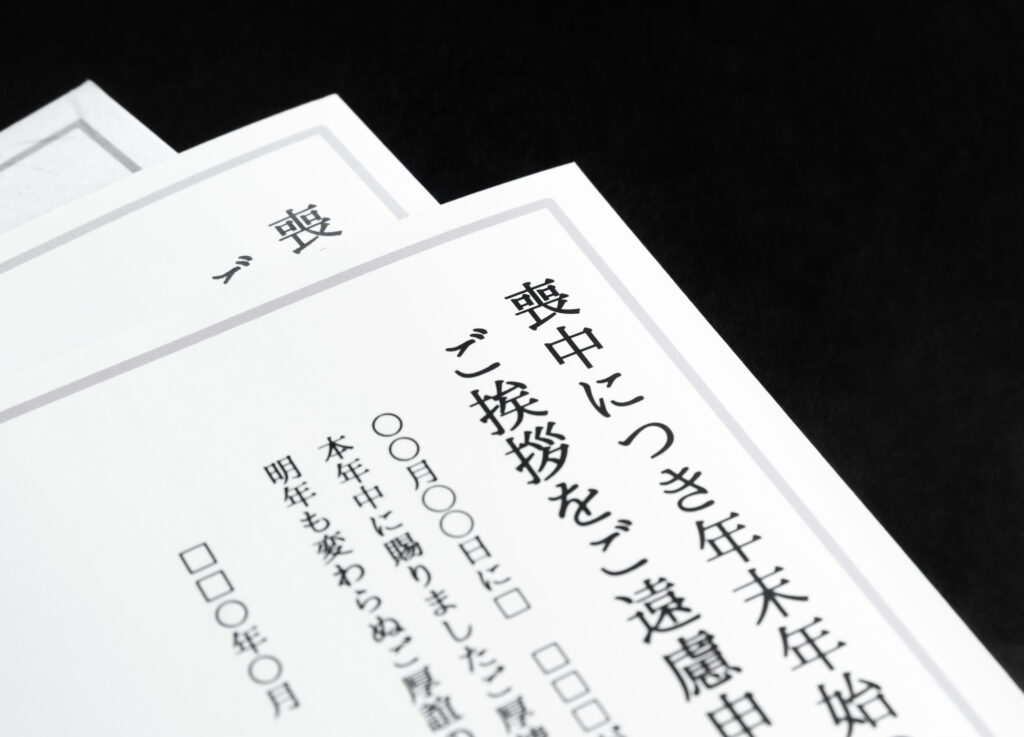
年始のご挨拶を控えるときの伝え方
喪中の期間に新年を迎える際、年賀状のやり取りを控えるのは故人への哀悼の気持ちを表すための礼儀とされています。年賀状を送る予定のある相手には、あらかじめ「喪中はがき」を出すことが一般的です。送付の時期は11月中旬から12月初旬が目安で、文面には故人が亡くなったことや新年の挨拶を差し控える旨を、簡潔かつ丁寧に記載します。こうした行動は、相手に無用な気遣いをさせないという思いやりのあらわれであり、自身の誠実さを伝えるものにもなります。
喪中はがきが届いた相手への対応
万が一、喪中はがきを出したにもかかわらず、相手から年賀状が届いてしまった場合でも、過度に気にする必要はありません。その場合は、松の内(1月7日)を過ぎてから「寒中見舞い」として、感謝の気持ちや近況を綴った葉書を送ると丁寧な対応となります。形式にとらわれすぎず、心を込めたやり取りを心がけることが、喪中における人とのつながりを温かく保つ方法です。
喪中が明けたあとの過ごし方と注意点

喪中明けの目安と考え方
一般的に喪中は、故人が亡くなってから一周忌までの約1年間とされています。ただし、宗教や地域によって異なる場合があり、仏教では四十九日、神道では五十日が「忌明け」とされます。形式にとらわれすぎず、家族の気持ちを大切にしながら、無理のないタイミングで日常に戻っていくことが大切です。
お祝いごとの再開は段階的に
喪が明けたからといって、すぐに華やかな祝い事に参加する必要はありません。まずは身近な行事から少しずつ再開し、結婚式や祝いの席への出席は、相手や周囲への配慮も忘れずに慎重に判断しましょう。心の整理ができてから、自然な形で復帰するのが理想です。
年賀状や正月行事の取り入れ方
喪明け後の年賀状は、前年の喪中への配慮として「昨年はご挨拶を控えました」と一言添えると丁寧です。おせち料理や正月飾りなども、無理をせず少しずつ家庭のペースで取り戻すことで、心にも負担なく過ごせます。
まとめ

喪中のお正月は、故人を偲びながら静かに過ごす時間です。正月飾りや年賀状、おせち料理などの祝い事を控え、家族で思い出を語り合ったり、お墓参りをしたりすることで、心を落ち着けて新年を迎えることができます。おせちに代えて控えめな料理を用意したり、ふせち料理を取り入れるなどの工夫も、喪中らしい配慮です。また、喪中はがきや寒中見舞いでの丁寧な対応も周囲への思いやりとして大切です。形式にとらわれすぎず、故人への感謝と今を大切にする気持ちで、穏やかな年始を迎えましょう。
香典返し・法要・法事の贈り物
香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」
香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。
カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。
ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。
>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」

























